梅雨を健康に過ごすために
6/8に九州北部の梅雨入りが発表されました。(平年より4日遅く、昨年より9日早い)
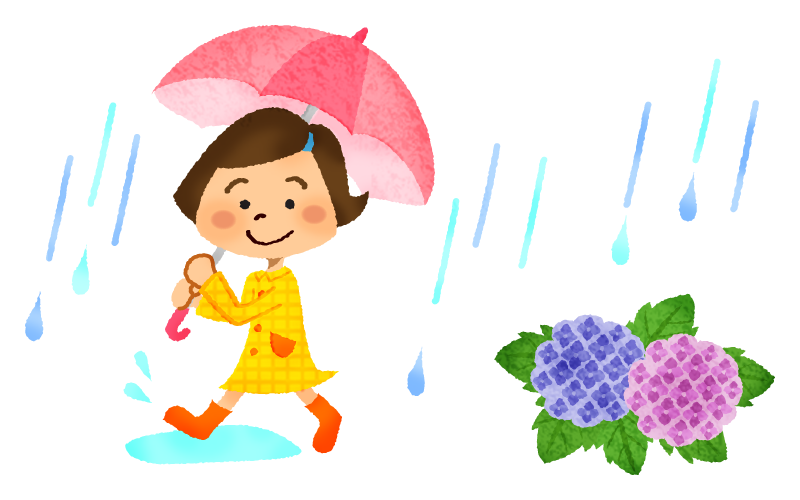
梅雨は「水の恵み」と同時に、体調を崩しやすい時期でもあります。
低気圧・高湿度・寒暖差・日照不足が重なり自律神経が乱れやすくなるため心身の不調を感じる方が増える傾向にあります。梅雨に起こりやすい体調不調と健康に過ごすためのポイントを紹介します。
梅雨に起こりやすい体調不良
- ・身体のだるさ・疲労感
- ・頭痛や肩こり
- ・食欲不振
- ・気分の落ち込み・イライラ
- ・睡眠の質の低下
- ・浮腫(むくみ)
これらは、自律神経の乱れや体温調整機能(ホメオスタシス)の低下によって起こります。気温の変化や湿度の高さに体がうまく適応できず、エネルギーを過剰に消費して疲れやすくなってしまうのです。
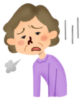
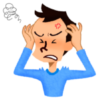

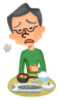

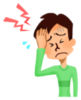
健康に過ごすための8つのポイント
-
-
① 朝型生活を意識する
朝日を浴び、朝食をしっかり摂ることで自律神経が整いやすくなります。
-
② 曇りや雨でも室内は明るく
気分の落ち込みを防ぐために、朝はカーテンを開けて部屋を明るく保ちましょう。
-
③ 就寝前に目元を温める
蒸しタオルやホットアイマスクで副交感神経を刺激し睡眠の質をアップ。
-
④ ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる(38〜40℃)
血行を促し肩こりやだるさの軽減に!片頭痛のある方はシャワーで済ませましょう。
-
⑤ 除湿を心がける
室内湿度は40〜60%が理想。除湿機やエアコンを活用しカビやダニの繁殖も防ぎましょう。
-
⑥ 食事で元気を取り戻す
- ビタミンB1:疲労回復(豚肉・玄米・大豆など)
- アリシン:ビタミンB1の吸収促進(にんにく・玉ねぎ)
- クエン酸:疲労・食欲不振の解消(梅干し・柑橘類)
- ビタミンC:ストレス対策(ブロッコリー・キウイ)
- カリウム:浮腫対策(バナナ・とうもろこし・芋類)
- たんぱく質:体力維持(肉・魚・卵・大豆製品)
-
⑦ 天気と気温のチェック
外出や出勤前に天気と気温差を確認し、羽織ものなどで温度調整をする。
-
⑧ 食品管理に注意
高温多湿で食中毒リスクが高まります。食品はすぐ冷蔵・冷凍しお弁当には保冷剤や保冷バッグの活用を忘れずに!
-
梅雨は農業にとって大切な季節ですが私たちの心身にも影響を与えやすい時期です。
梅雨の体調不良は誰にでも起こりうるものです。生活リズムを整え、栄養バランスを意識し、梅雨に負けない元気な体をつくっていきましょう。



2025年06月09日 更新

 0977-24-3310
0977-24-3310